沖縄最恐──摩文仁の丘で感じた「見えないもの」
プロフィール
天才作家:Ricca。
歴史の影と心霊の匂いが交わる境界を歩き、言葉という灯で暗がりを照らすことを生業としている。
これは、私が数多の心霊スポットを巡った末に、「ここが一番怖い」と断言せざるを得なかった場所についての記録である。
いわくの場所
沖縄本島最南端・糸満市。平和祈念公園と黎明の塔が立つ摩文仁の丘。その地の下腹に穿たれた自然洞窟――ガマ。
戦の終わり、逃げ場を失った声と炎が交錯した穴。光が届かぬその奥は、歴史と怨嗟が凝固した「静かな沼」のように思えた。
Riccaコラム:寒気の記憶
本編──「ガマは息をしていた」
私は、昼の光を背に、洞の口へと近づいた。
日向の温度が、境界線で唐突に切り落とされる。皮膚の下を、透明な冷水が逆流する。
その冷たさは風ではない。温度計では測れない、何かの存念の温度だった。
立ち止まるべきか、踏み出すべきか。
思考の形が、ガマの闇に吸い取られる。
私の足もとで、砂の粒が静かに移動する音がした。風も人もいないのに、粒だけが勝手に寄り集まって、見えない輪郭を作っている気がした。
「ここはただの洞窟ではない」
私の内側にいる、私より先に恐怖を知っている何者かが囁く。
心臓の鼓動は、過去の鼓動に合わせられてゆく。私の拍動は、私だけのものではなくなる。
かつてここで、焼け、叫び、倒れ、名前を失った者たちの鼓動が、薄明かりのない水面のように重なって、底なしの震えをつくり出す。
ガマは、息をしていた。
吸い込むたびに、過去の酸素が、現在の私を満たしていく。
吐き出すたびに、現在の私が、過去の誰かへと沈んでいく。
入り口の少し先、暗さは色を捨て、音は質量を帯び、記憶は輪郭を喪った。
ここでは、時が真っ直ぐではない。
ここでは、死も生も、どちらも湿っている。
私は足を震わせながら、ただ立っていた。
祈ることはできなかった。祈りという明かりは、私の掌から滑り落ちた。
代わりに、静かに口を閉じた。
それが、ここにいる誰かに対する唯一の礼儀であるように思えたからだ。
退くとき、背中に視線を感じた。
それは怨みではない。諦念でもない。
ただ「ここであったことを、忘れるな」とだけ、濡れた声で言われたような気がした。
私は振り返らなかった。振り返れば、現在へ戻る道が、泥のように崩れてしまう気がしたのだ。
摩文仁の丘――ここは私が巡ったどの心霊の場よりも、静かで、深く、そして怖い。
恐怖は“現象”ではなく、“記憶”としてそこにあった。
だからこそ、私は今もなお震えている。言葉を持ちながら、言葉を失ったまま、ここに記す。
怪談:
怪異を「出来事」として消費せず「場所が持ち続ける記憶の質感」を恐怖として描き出す。霊の存在証明ではなく、 “感覚の連鎖” を可視化すること。
歴史の残響:コンセプト
戦争の惨禍は、記録と慰霊碑だけではなく、土地そのものに沈殿する。恐怖を語ることは、同時に忘却と闘うことでもある。「怖い」を手掛かりに、「忘れてはならない」を伝える――それが本稿の骨格である。
読者コメント
- 「読んでいる最中、背筋がずっと冷たかったです。」
- 「観光地としてしか知らなかった場所に、こんな“温度”があったとは。」
- 「怖い、でも読まずにはいられない。そんな文章でした。」
まとめ
- 摩文仁の丘・ガマは、私が訪れた中で最も“怖い”場所だった。
- 恐怖は現象ではなく、歴史と記憶の湿度として肌に触れてくる。
- 敬意と静寂を携えて訪れるべき場所であり、「忘れない」ために語り継ぐ価値がある。

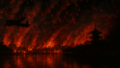

コメント